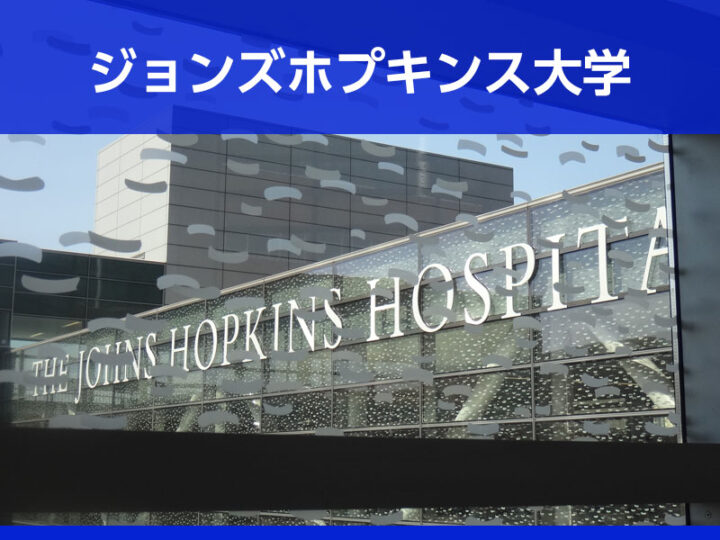一部の肺がんで放射線療法が免疫療法抵抗性を克服
ジョンズホプキンス大学キンメルがんセンターのブルームバーグ・キンメルがん免疫療法研究所とオランダがん研究所の研究者らによる新たな研究によると、放射線治療は免疫系を活性化させることにより、免疫療法に抵抗する特定の腫瘍を治療に対して影響を受けやすくし、患者に良好な治療結果をもたらすことが明らかになった。この研究は米国国立衛生研究所の支援を受けている。
Nature Cancer 誌に7月22日に発表されたこの研究では、研究者らは非小細胞肺がんの分子生物学を深く掘り下げ、放射線療法に免疫療法薬を併用した場合、あるいは免疫療法薬単独で治療した場合に、細胞レベルおよび分子レベルで、時間の経過に伴って何が起こるかを突き止めた。その結果、通常、免疫療法薬に反応しない肺がんでも、放射線治療と免疫療法薬を併用することにより抗腫瘍免疫反応が身体の様々な場所で誘発されることが判明した。また、免疫療法抵抗性(免疫療法が効きにくい状態)の特徴を内在的に持っている腫瘍を有する患者においても、併用療法により臨床成績の改善がもたらされた。
臨床的に、この結果は放射線療法が、特定の患者において免疫療法抵抗性を克服するのに役立つことを示唆している。
「治療効果が期待できない肺がんの一部では、放射線療法は免疫療法に対する一次耐性を回避するのに特に有効かもしれません。このことは、潜在的に獲得耐性に対しても適応できる可能性があります」と統括研究著者である Valsamo "Elsa"Anagnostou医学博士(上部気道消化管悪性腫瘍プログラム共同ディレクター、胸部腫瘍学バイオリポジトリ・ディレクター、精密腫瘍学における分析リーダー、ジョンズホプキンス分子腫瘍会議共同リーダー、ジョンズホプキンス肺がん精密医学卓越研究拠点共同リーダー)は述べる。
研究者たちは、一部の腫瘍が免疫療法(がん細胞と戦うために身体自身の免疫システムを活用する治療戦略)に対して抵抗性を示す理由とその抵抗性を阻止する方法をより詳しく理解しようと長年にわたり探究し続けている。
放射線治療は、アブスコパル効果と呼ばれるユニークな現象から、全身的な免疫反応を誘導する一つの可能性として提案されてきた。原発性腫瘍の部位に放射線を照射すると、通常、腫瘍細胞は死滅し、その内容物が局所の微小環境に放出される。時には、免疫系がそれらの内容物を発見し、腫瘍の分子的足跡を学習したのち、体中の免疫細胞を活性化させ、体内の原発性がんから遠く離れた場所など放射線の標的ではなっかた腫瘍部位のがん細胞を攻撃する。
この効果により、放射線治療は、放射線部位から遠く離れたがんに対しても、免疫療法の効果を向上させる可能性がある。しかし、アブスコパル効果の分子生物学的メカニズムや、いつ、どのような患者にアブスコパル効果が起こるかを予測する方法については、これまでほとんど知られていない。
この現象を研究するため、Anagnostou氏らは、治療期間中のさまざまな時期に、原発巣だけでなく体内のさまざまな場所から肺がん患者のサンプルを採取した。彼らは、オランダがん研究所の Willemijn Theelen 氏、Paul Baas 氏と共同で、放射線療法後の免疫療法、特にPD-1阻害剤ペムブロリズマブ(販売名:キイトルーダ)の効果に関する第2相臨床試験を実施した。
Anagnostou氏のチームは、Theelen氏とBaas氏の協力を得て、ベースライン時と3~6週間の治療後に72人の患者から採取された293の血液と腫瘍サンプルを分析した。対照群の患者らは免疫療法薬のみを受け、実験群の患者らは放射線療法後に免疫療法薬を受けた。
研究チームはその後、マルチオミクス解析(ゲノム解析、トランスクリプトミクス、さまざまな細胞分析など異なる「オミクス」ツールを組み合わせた解析)を行い、放射線を直接照射していない腫瘍部位の全身および局所の微小環境で、免疫に何が起こっているのかについて詳細な特徴を明らかにした。
特に、研究チームは免疫学的に「冷たい」腫瘍、すなわち一般的に免疫療法に反応しない腫瘍に焦点を当てた。このような腫瘍は、変異が少ない、PD-L1と呼ばれるタンパク質が発現していない、Wntと呼ばれるシグナル伝達経路に変異があるなど、特定のバイオマーカーによって認識が可能である。
研究チームは、放射線療法と免疫療法の後、放射線照射部位から遠く離れた「冷たい」腫瘍では、腫瘍微小環境が顕著に変化することを確認した。Anagnostou氏は、この変化を腫瘍の「ウォーミングアップ」と表現し、免疫活性がほとんど、または全くない状態から、新しいT細胞や既存のT細胞の増殖を含む強い免疫活性を持つ炎症部位へと移行したと説明している。
「私たちの知見は、免疫療法薬単独では奏効しにくい肺がんにおいて、放射線がいかに全身の抗腫瘍免疫反応を増強することができるのかを明確にするものです」とマルチオミクス解析を主導した筆頭研究著者Justin Huang 氏は述べる。「私たちの研究は、がん生物学の知見の臨床応用においての国際的、学際的な共同研究の価値を強調するものです」。Huang氏は、ジョンズホプキンス大学医学部の若手研究者らとその指導教員による画期的な発見が評価され、2025年のポール・エーリック研究賞を受賞した。
Anagnostou氏の研究チームは、ジョンズホプキンス大学キンメルがんセンターの腫瘍学准教授でブルームバーグ・キンメルがん免疫療法研究所の研究員であるKellie Smith博士とともに、放射線療法と免疫療法薬の併用で長期生存を達成した患者に焦点を当て、患者自身のT細胞が体内でどのような働きをしているかを調べる機能試験を行った。
最後に、研究チームは、臨床試験から得られた患者の治療効果を追跡することにより、免疫学的に冷たい腫瘍を有する患者が、放射線療法によって(腫瘍が)「ウォームアップ」し、放射線療法を受けなかった患者より治療効果が良好であったことを確認した。
「研究は大変興味深いものでした。紆余曲折が研究結果に本当に重要な役割を果たしました」とAnagnostou氏は述べる。「私たちはアブスコパル効果を捉えただけでなく、免疫療法に対する反応が期待できないような腫瘍においても、免疫反応と臨床成績を関連付けることができたのです」。
同じ患者集団から採取した検体を用いて、研究チームは最近、血液中の循環腫瘍DNA(ctDNA)を検出することにより、免疫療法に対する身体の反応を捉えることに取り組んでいる。この研究は、4月28日に、シカゴで開催された米国がん学会年次総会で発表された。
本研究のその他の共著者は以下のとおりである(敬称略)。Zineb Belcaid, Mimi Najjar, Daphne van der Geest, Dipika Singh、Christopher Cherry, Archana Balan, James R. White, Jaime Wehr, Rachel Karchin, Noushin Niknafs and Victor E. Velculescu. ラドバウド大学医療センターのMichel M. van den Heuvel 氏も貢献した。
本研究は、ジョンズホプキンス大学ブルームバーグ・キンメルがん免疫療法研究所、および米国国立衛生研究所の支援(助成金番号 CA121113)を受けた。
その他の開示情報については原文を参照のこと。
DOI: https://doi.org/10.1038/s43018-025-01018-w
- 監修 高濱隆幸(腫瘍内科・呼吸器内科/近畿大学病院 ゲノム医療センター)
- 記事担当者 山口みどり
- 原文を見る
- 記事掲載日 2025/7/22
【免責事項】
当サイトの記事は情報提供を目的として掲載しています。
翻訳内容や治療を特定の人に推奨または保証するものではありません。
ボランティア翻訳ならびに自動翻訳による誤訳により発生した結果について一切責任はとれません。
ご自身の疾患に適用されるかどうかは必ず主治医にご相談ください。
肺がんに関連する記事
米FDAがHER2 TKD活性化変異陽性の肺がん(NSCLC)にゾンゲルチニブを迅速承認
2025年8月14日
肺がんの術前ニボルマブ免疫療法+化学療法は長期生存を有意に改善
2025年8月4日
進行ステージIII非小細胞肺がんに対する化学免疫療法戦略の有望性
2025年7月24日
米FDAがEGFRエクソン20挿入変異を伴う転移非小細胞肺がんにsunvozertinibを迅速承認
2025年7月7日