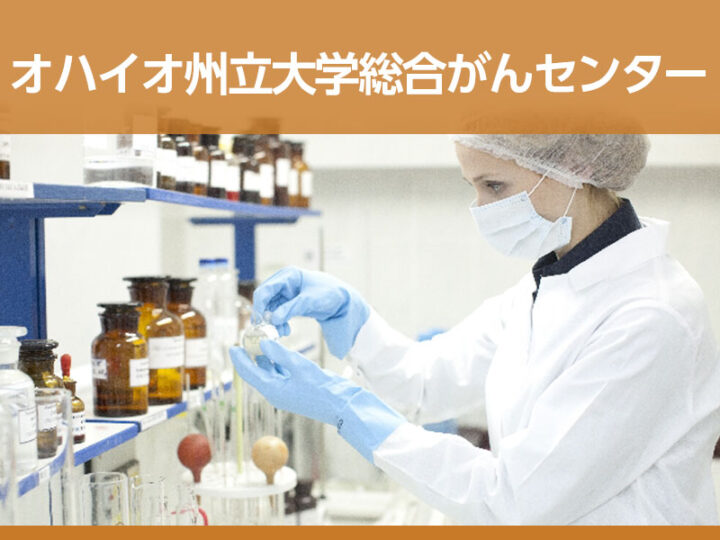【AACR2025】進行固形がんで組織+液体生検に基づく個別化治療で転帰改善の可能性
両方の検査に基づいた治療は標準治療よりも転帰を改善
進行固形がんの患者が、組織生検と液体生検(リキッドバイオプシー)の両方で同じゲノム変化が検出されることに基づく個別化治療を受けた場合、標準治療やいずれかの生検のみに基づく個別化治療を受けた場合と比較して、生存結果が大幅に改善された。これは、4月25日から30日に開催された米国癌学会(AACR)2025年年次総会で発表された第2相多施設共同ROME試験の結果である。
ゲノムプロファイリングは、個別化医療の一環として用いられており、治療の標的となる腫瘍における一部の変化を特定する上で役立つ。検査は血液や組織サンプルを用いて実施できるが、臨床現場ではどのような状況下でどちらの方法が優先されるべきかは依然として不明であると、イタリア・ローマの皮膚病理学研究所(IDI-IRCCS)の科学ディレクターであるPaolo Marchetti医師は述べている。
組織生検では腫瘍から検体を直接採取するが、侵襲的な外科手術が必要である。検体は腫瘍の一部の部位から採取されるため、腫瘍の他の部位の変異を見逃す可能性がある。一方、リキッドバイオプシーで必要なのは血液検体のみであるが、血流中に十分な細胞が放出されない腫瘍の変異を検出できない可能性がある。このような検体採取方法の違いが、結果の不一致につながる可能性がある。
「組織生検とリキッドバイオプシーにおける分子変化の不一致を調査することは、個別化医療にとって極めて重要です」と、試験結果を発表したMarchetti医師は説明した。「部位によって腫瘍の特徴が異なり、臨床的に有効な標的も異なる可能性がありますが、現在の生検戦略では、こうした不均一性を捉えきれないことがよくあります」。
2020年11月から2023年8月の間に、進行または転移性固形腫瘍を有し、二次治療または三次治療を受けている成人患者1,794人がROME試験に登録された。各患者は、液体(FoundationOne Liquid CDx)と組織(FoundationOne CDx)の両方の生検検体を提供する必要があった。検体に対し、次世代シーケンシングが実施され、その結果は分子腫瘍委員会によって分析され、治療可能と判断される変化に基づいて一致と不一致の両方が評価された。一致とは、両方の生検検体で同じ重要な変化が検出された場合と定義され、不一致とは、一方の生検検体でのみ検出された場合と定義された。同委員会は、個別化治療の標的となり得る変化を持つ患者400人を特定した。
これら患者400人のうち、組織生検とリキッドバイオプシーで同一の治療可能な変化が認められた症例は49.2%(197人、T+L群)であったのに対し、組織生検のみで治療可能な変化が認められた症例は34.7%(139人)、リキッドバイオプシーのみで治療可能な変化が認められた症例は16%(64人)であった。各群において、患者は担当医の選択に基づき、個別化治療または標準治療のいずれかに無作為に割り付けられた。
全生存期間(OS)の中央値は、個別化治療を受けたT+L群で11.05カ月であったのに対し、標準治療群では7.7カ月であり、T+L群の患者の死亡リスクは26%減少した。これらの群の無増悪生存期間(PFS)の中央値はそれぞれ4.93カ月と2.8カ月であり、T+L群では増悪リスクが45%減少した。一方、個別化治療の生存利益は、結果が一致しない患者ではそれほど顕著ではなかったか、まったくなかった。全体的に、OSはT+L群(11.05カ月)の方が長く、次いで組織生検群(9.93カ月)、リキッドバイオプシー群(4.05カ月)の順であった。PFSも同様のパターンで、PFSが最も長かったのはT+L群(4.93カ月)で、組織生検群では3.06カ月、リキッドバイオプシー群では2.07カ月であった。
さらに、12カ月生存率は、個別化治療を受けたT+L群で47.8%、標準治療群で38.8%であったのに対し、12カ月無増悪生存率はそれぞれ27.2%と9.1%であった。T+L群における客観的奏効率は、個別化治療群で20%、標準治療群で11.8%であった。
「生検所見が一致した患者で観察された優れた転帰は、分子プロファイリング手法を組み合わせることで、患者選択を最適化し、個別化治療を最適化する可能性を浮き彫りにしています」とマMarchetti医師は述べた。「この一致は、腫瘍が異なる転移部位で同じゲノム変異を発現していることに関係している可能性があります。疾患のサブタイプ、転移部位、生検部位など、より多くの因子を考慮して解析を拡大することで、より効果的な新たな診断経路を確立できる可能性があります」。
不一致症例の原因は、分子変異の検出における不一致(43.3%)、遺伝子変異量の多さ(35%)、マイクロサテライト不安定性(1%)、および検査不良(21%)であった。不一致率が最も高かった2つの経路は、PI3K/PTEN/AKT/mTORとERBB2であった。
Marchetti医師は、不一致に対処するための戦略を策定する必要があると述べた。例えば、追加の分子プロファイリング手法の導入、既存の技術の感度と特異度を高めることである。同医師の研究グループはまた、多施設コホート研究において、連続した時点での液体と組織の統合プロファイリングを用いて、これらの知見を検証する予定である。
「不一致の課題に対処し、両方の生検法の長所を活用することで、将来の戦略は個別化医療のアルゴリズムを改良し、進行がん患者の臨床転帰を向上させることができます」とMarchetti医師は述べた。
本研究の限界としては、解析が探索的であること、およびサブグループ比較において事前に定義された統計的検出力がないことが挙げられ、これらが結果の一般化可能性を制限している。組織生検とリキッドバイオプシーの検体は異なる時期に採取されたため、結果に影響を与えた可能性がある。さらに、特定のサブグループ、特にリキッドバイオプシーのみの群は比較的規模が小さいため、これらの集団に対する結論の頑健性に限界が生じる可能性がある。
*本研究の情報開示については、原文を参照のこと。
- 監修 高濱隆幸(腫瘍内科・呼吸器内科/近畿大学病院 ゲノム医療センター)
- 記事担当者 仲里芳子
- 原文を見る
- 原文掲載日 2025/04/29
【免責事項】
当サイトの記事は情報提供を目的として掲載しています。
翻訳内容や治療を特定の人に推奨または保証するものではありません。
ボランティア翻訳ならびに自動翻訳による誤訳により発生した結果について一切責任はとれません。
ご自身の疾患に適用されるかどうかは必ず主治医にご相談ください。
がんに関連する記事
胸腺の健康状態ががん患者の免疫療法の効果と関連
2025年11月6日
米国癌学会(AACR)年次報告書2025、がん研究への連邦投資の救命効果を強調
2025年10月17日
がん関連神経傷害は慢性炎症と免疫療法抵抗性をもたらす
2025年8月28日
がんの不安は患者本人以外にも及ぶ
2025年7月31日